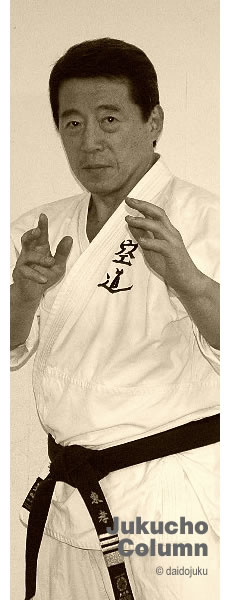
スペイン有数の格闘技雑誌、EL BUDOKA(http://www.editorial-alas.com/)に空道、大道塾を紹介する記事を書いて欲しいとの要請により寄稿したもの。
技術の伝承”について
昔の剣術の稽古は,当然、木刀(もしくは稀に真剣)によるいわゆる“寸止め”での練習しか出来なかった。敢えて木刀での打ち合いをした流派も有ったようだが,これでは当然、ほんの一握りの先天的な才能の有るものしか残れないので,世に出る、知名度の有る大きな組織には成れなかっただろう。千葉周作により竹刀が発明されたことで、実際に当てながらの試行錯誤が出来るようになり,技術は急激に進歩した。しかし、これも長短があり、竹刀は前二者に比して当然軽いので中には実戦では使えない技が生まれ、 “竹刀剣道”とか“早当て競技”という蔑称も生まれたが、型稽古だけの固定した技より、実際に打ち合い,受け合う中での技の習得という利点の方が大きかったのだろう、実際の殺し合いが頻繁に行われた幕末の実戦の中でも生き残った。
例外というかもう一つの稽古方法として(素手の場合もそうだが)実際の闘いおいては,気力,気迫というものも勝敗の半分以上の割合を占めるものだから、横にした竹(?)の束に,“肉を切らせて骨を断つ”という様に、身を捨てて遮二無二(恐怖心を振り払って)思いっきり打ち込むだけの稽古をした“薩摩示現流”という流派が、幕末の殺し合いの時には凄まじい威力を発揮し、一躍「薩摩示現流,恐るべし!」となった。闘い方は「チェーストー!」と,身を捨てるようにして、体ごと相手にぶつかって袈裟に切り下げるだけの単純な刀法だったらしいが、相手はその奇声と決死の突進に恐れをなし逃惑い討取られたという。(しかし、その“殺し合い”の時代を過ぎれば、やはり“早当て競技的”試合ではその実力を発揮は出来にくいので、普及という点では難しいのだろう,今では元の「型稽古」の流派となった。)
このように通常今までの“闘技は”創始者の経験から生み出された技の応酬を公式化し、相手がこう打って来たなら、こう受けて、もしくは“かわし”てこう切り返す、といったような方法にしろ、 薩摩示現流のような対人練習でないにしろ、兎に角、同じ動作を無限に正確に出来るよう反復練習をするものだった( “型” )。この方法は一定レベルの人間を生み出すには効率的な方法だし、相手に当たれば切れる“剣”を使うのだから、打つ(切る)人間に多少の腕力の違いはあっても、大概は相手に傷害を与える事が出来るから、剣術に関しては充分に意味の有る重要な方法ではある。
しかし一方、この方法は習う人間が創始者と同じような個性(身体的、性格的)の場合は、その人間にとっては最高の方法となるだろうし、手っ取り早く上達もするが、そうでない場合は全く同じ事をする事を至上のものとする所から、個性の違うものに対しては、「“つの”を矯めて牛を殺す」式になる可能性が大きいし、当然、創始者のレベル以上のものにはならない。これが“型”の弊害だ。
しかし、今回の“型”はそういう意味ではなく、いわゆる空手独自の、一人でやる一連の動きの事を言ってるのだと思う。相撲や柔道のように、投げられてもそれほど大きなダメージにはならなず(勿論、頭から固い所に落したり逆関節を極めたりすれば重大な怪我を招くが)気軽に技の交換が出来る“組む闘技”と違い、空手や剣術の勝負は“制空権“を必要とする “排撃的な闘技”であり、技の応酬に“速さ”を要求されるので、瞬間瞬間の反射神経の勝負であり,神経を張り詰めないと出来ない。更に空手は(剣術も)“打撃”であるから、当れば痛いので技の交換などは中々気軽に出来ない。
空手が日本に入った明治初期の頃は、気軽に素手で打ち合える防具もなかったので、空手はそれを逆手にとって、相手に当てないで寸前で止めて形やタイミングで勝敗を競う“寸止め”という方法を生み出した。しかもその上に、個人でも出来る、ここで言う“型”という上手い練習方法も生み出した。即ち、創始者の経験の中から、敵との技の応酬をシミュレーションして、それに対して決まりきった受けや攻撃の技を連続的に出して現実性を待たせたり、立ち居振舞いに迫力を出し、“武道的形式美”を表現したりするようにしたのだ。
実際、蹴り等を出す難しさは“見る者”も、自分に置き換えて実感しやすいから“鍛練”を感じるし、“やる方”も大きなダメージなしに擬似的攻防を練習でき、それが他人への強い示威行動にもなるので自己満足できるので、この方法は空手の普及に大いに役立ち空手は一気に広がった。
しかし、ここで忘れてはならないのは、空手に限らず武器を持たずに、自分の肉体のみで闘う“素手の武道,格闘技”の場合,まず同じ形の技を使っても,使う人間の主に身体能力の差で,動きに大きな差が出るし、当たっても剣のような“刃物”ではないから、相手に与えるダメージも一様には出ない。当れば倒れるはずだとの思い込みにより、普段当てていない拳では、相手の体力によっては効かない場合も出て来る。しかも相手も(ある一定の個性を持った)創始者を相手にした時と同じ動きをするとは限らない。そうなると却って創始者の経験から生み出された、決まりきった一連の動きにとらわれる事は,臨機応変な(自由な)判断と反応、研究、応用を殺してしまう。
それより、今は視界が広く、“素手”でも当てても良い、軽量の防具があるのだから 実際に当てる攻防の応酬を自由自在にした方が、技の向上も著しいし、当っても効かない場合には体力を付ける必要性も感じるので鍛錬もするので、より現実的(実戦的)になる。これが今まで大道塾が“型”をしなかった基本的な理由だ。
“体育教育”
しかし一方の“体育教育”という観点からは、“型”の存在に大きな意味がある事は設立当初から分ってはいた。(拙書「格闘空手2」‘86年初版、P149「“型”の意義の一考察」収録)。なぜなら、大道塾はそのスタートに、現実に有効性のある“護身の技”を追求するのが大きな目的の一つではあるが、一方、単に強さのみを求めるのではなく、「社会人の自己実現力の向上」と「青少年健全育成」といった真に社会に役立つと認められ得る「社会体育」という理念をも重視してきた。
その為、当時「壮年部」といわれていた年代のクラスを「ビジネスマンクラス」として一般部と同様に重要視した結果、他団体に比べてかなり充実したクラスとなっている。しかし社会の高齢化と共に当時40歳台だった第一期の塾生たち50歳を越えて来ているが「若い時と同じ百点満点の組み手が出来ないから鍛錬は意味がない、やっても無駄だ」ではなく、当然、幾つになっても護身術の必要性はあるし、健康を維持する上でも“型”などは無理なく習慣的に体を動かす事につながり、中高年特有の病気(糖尿病や、高血圧、心臓病など)への予防的意味もある。
また、少年部の興味の維持にとって、“型”は身体能力、センス、といったものが重んじられる“組み手”と違い誰でも一定のレベルにはなれるので継続しやすいし、決まりきった事を習得する為に、指示に従う習性が付く,従って年長者を尊敬するようになる、といったように、今、世界のどの国でもが悩みの種である青少年の躾や教育の手段としても非常に有効な練習方の一つである。そういう意味で“型”はビジメスマンには“技と体力、健康の維持”に気軽に出来る、いわば“武道健康法”として、少年部には“躾、教育”の意味で大きな意味がある。
また、かつて合理的な欧米人からは、「型などは実戦では役に立たない」として無視された(確かに従来の“型”が実戦では大して役には立たないのは事実だろうが)しかし近年、長い歴史に洗練されたそれらの“型”を“東洋的な独自の形式美の世界”として理解している層も出てきており、前述の一定程度の実用的な部分とあいまって、以前ほどの拒否反応はなくなった。
型の存在意義は分ったにしても、大道塾にとっての問題は現行の“型”が所謂“三戦立ち”や“厳密な意味での前屈立ち”で構成されている事だ。基本の突きは大道塾の“組みて立ち”でしているのに、“型”の時は寸止め(伝統派)の、腰から出す突きを使ったのでは全く “様(さま)”にはならない。その基本を身につけるにも少なくとも500から1000時間は掛かるはずで、しかもそれなりに見られるようになったとしても, 少年部がやるのは愛嬌としてまだしも,一般部やビジネスマンがやる場合は、 伝統派ならではの“雰囲気”なり“微妙な感覚”は身に付かないから“猿真似”をしているとしか見えず“形式美”どころではない。
“型”の効用は認める、しかし所詮”猿真似”としてしか評価されない。それならば、大道塾の基本を元にした自前の“組み立ちからの実戦型”を作る必要がある。しかも従来のような一連の技の連続ではなく、選手として実際に自分が試合や実戦の中(対人)で使った技の応酬でだ。それなら、現実の証明もされているし、年齢を重ねても無理なく指導できるし、自分の体を動かす事にも繋がる。
そこで今、北斗旗の歴代の優勝者への顕彰として“大道塾の型”を創る権利を与えている。しかし、中々この“型”を創作する意義を突き詰めていない“型絶対反対派(実戦あるのみ派?)”や、意義は分っていても、「自分なんかが型を創るなんてとんでもない」と、既に“型”としては歴史と権威のある“伝統型”に拘る者などなどの考えがあり、実現していないのは残念な事だ。
こういうものは強制して創らせたって良いものが生まれるわけはないので、私もそのままにしているのだが、該当者には良く考えて欲しい事がある。即ち、伝統を重んじるとか、謙虚な姿勢というのも分るが、今は伝統的なものとして伝えられている“型”だって、始めは革新的だったり、試行だったりしたのだ。物事と言うものは(「北斗旗」もそうだったが)無数の試行の中で、歴史の検証に耐えたものだけが残り、そうでないものは忘れ去られるのだと考えれば、何も事をそれほど大仰に考える事はないのだ。逆にそうだと思えば、自分のこれまでの“組み手”を改めて充分に吟味して、歴史の評価に耐えるような素晴らしい、“型”を研究、創作して欲しいものだ。
