
RE:
RE:
今は伝統派とフルコン派が「別なスタイル、別なルールの空手]ということで、ある程度棲み分けていますが、私が選手だった30数年前ころには「どっちが本物だ!」みたいな完全な対立状態でした。
ご存じのように私は、様々な流派のある古流柔術から生まれて「一つのルールで確立された柔道」から空手界に飛び込みました。その為、当時各方面で活躍していた柔道の同期にも負けたくなかったので、「格闘技としても通用する空手」という目標から「格闘空手 大道塾」という名称を使いました。
しかし、「競技人口では武道界隋一と言っていい空手道の評価がもう一つなのは、群雄割拠と言えば聞こえはいいが、流派団体が乱立しお互いに足の引っ張り合いをしているからだ」と考えるようになっていたので(※)「不毛な対立は避けてなんとか『同じ空手道』ということで協調し合えないものか」と思っていました。
※:それについては拙著「はみ出し空手から空道へ」(福昌堂刊)で考察しています。
その上に、大道塾設立当時は、将来的には別な仕事をしようとしていたので、一時は単純に闘う道で「闘道」等という名称も考えましたが、当時、確執のあった編集者から漫画の中で悪役として使われてからは、余計な面倒を増やしたくなかったし、ましてや「柔術から生まれた柔道」というように「空手から生まれた空道」などと、それこそ夢にも考えなかったから、道着にはあえて流派名は入れなかったのです。
所が設立後1年位してからでしょうか、内弟子の一人に「柔道と違い空手に流派・団体が多くあるというのは既にみんなが知っていることです。逆に『空手道』だけでは『どこの空手ですか?』と聞かれるし、後輩を引っ張る時の強い団結力や求心力はいつまで経っても生れないんじゃないですか?」と言われました。 実際、知らない人に聞かれて「こういう考えの、こういうルールの空手団体です」と一々答えるのも煩わしく、現実問題として無名の団体への入門者も減り始めて来たり、設立当時は残った弟子も少しずつ脱落し始まったので、妥協策、現実策として団体名を強調することにしたのです。
序(ついで)に言うと、今は逆に「なぜ胸に団体名を入れないのですか?」と聞かれます(笑)
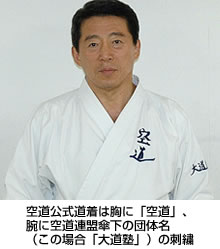 理由は、上記の理由で20年間「格闘空手」という理念で活動してきましたが、「突き・蹴りの空手」に、初めは存在していた投げや締めも加えただけで「いわば先祖がえりをしてるのだ」と言っても、空手が沖縄から日本に輸入されて約100年。柔道との棲み分けで「突き・蹴りが空手」で「投げ締め関節は柔道」という既成概念は強く、私の「空手への想い」とは別に「あれは空手じゃない」と言われることが多くなってきました。
理由は、上記の理由で20年間「格闘空手」という理念で活動してきましたが、「突き・蹴りの空手」に、初めは存在していた投げや締めも加えただけで「いわば先祖がえりをしてるのだ」と言っても、空手が沖縄から日本に輸入されて約100年。柔道との棲み分けで「突き・蹴りが空手」で「投げ締め関節は柔道」という既成概念は強く、私の「空手への想い」とは別に「あれは空手じゃない」と言われることが多くなってきました。
また、「すぐに潰れる」と言われながらも、幸いにして世界大会を開いて欲しいという声が、主に海外から挙がるまでになれたのですが(国内では日本人の常として「時期尚早」でした笑)、当時、空手の大きな世界大会が既にいくつかありましたから、「ここでまたウチが空手の名前で世界大会をしたのでは、よけい空手界の混乱を印象付けるし、引いては日本武道のためにもならない」と、浅学菲才の身を顧みれば「無謀、傲岸!」と言われるのは重々承知の上で、「空道」という”暴挙”に出たのです(笑)。
今考えると本当に「よくもあんなことをしたものだ」と怖くなったり、「ここまで武道にのめり込まなければ、俺には別な人生があったんじゃないのか・・」と複雑な気持ちになる時もありますが・・・・。
閑話休題。そうなると道場(団体)名「大道塾」は座右の銘「大道無門」からとった言葉なので変える気はなかったのですが、道着の胸の名前が同じ「大道塾」では、たとえ「新しい技術体系の武道を試行する」という気概で行動しても表面的には何の変化もなく「空手なのになんで掴んだり寝技をしたりするんだ!?」などと余計な誤解も招くので、それこそ上記と逆の意味で、空手ではありませんと「主義主張を一々説明する」必要があります。それよりは「空道」という名を使った方が、「試合のルールも極端に違うし、名称も違う」とスンナリ理解をして貰い易いだろうと結論したからです。
更に言えば、個性の強い人間が集まる武道・格闘技界では様々な理由(※)から団体の分裂、乱立は常に起きる可能性があり、ある程度の年月を経て社会的認知を得るまでになった競技・団体のいくつかが、「ある日突如として分裂!」ということの繰り返しで、結果として斯界(業界?)の”縮小再生産”を印象付けているのは残念なことです。
※:「滅び (地獄へ) の道は善意というレンガで敷き詰められている(ダンテ「神曲」煉獄編」で、純粋とも言えるのだろうが「自分の武道観を実践したい」と猪突猛進するか、単に自我が強くて「上と気が合わない」、果ては自分が一番でありたいという「自己顕示欲」等々。
そんな事情でも、特に空手界に団体の分裂乱立が起きやすいのは、もっと人間関係が濃密で信頼関係をもとに成り立っていた昔の空手(武道)家には、名前を法的に守るなどという発想はなく誰も「商標登録」をしていなかったので「空手」という言葉は誰でも使えるからです。極端な話、ある団体を辞めても次の日には別な空手の団体を設立できるのです。
そうなれは前述したような武道・格闘技の根本的な体質に加えて、個人的には「苛められた」とか、「弱いから」という動機が一番多いだろう空手を始める人間は一般的に、感受性が強い(情が強い、感情豊かとも言える) 急な攻撃に急な反応を要求される競技性で養われる直情径行型の言動も相まって、余計に拍車がかかるのです。(中途半端だの何だのと言われながらも、突き蹴り主体の空道に組技を入れたのも格闘技的観点だけではなく、打撃系武道家のそういう性向をも緩和したかったからです)
そして果ては「裏切った」だの「師範 (先生、先輩)は変わった」だのという互いの立場からだけの罵り合いが続くのです・…。暫くして自分も同じ立場になって「師範(先生、先輩)の気持ちが分かるようになりました」と続くのですが、一旦割れてしまった茶碗は大抵は元に戻す事はできないのです。
そういう”人世模様”や”人間関係”、それらに伴う様々な”政治” を見てきて、そういう状況は弟子には味あわせたくない、武道の本来の目的「心身の向上」に専念させたいとの想いで、あまり気が進みませんでしたが「空道」や[大道塾]、[北斗旗]という言葉を法的に守るようにしました。
そんな訳で、大道塾にも残念ながら今まで何人か縁の切れた人達がおりますが、彼らは「空道」という言葉は使えないので空道に分裂や乱立といった、現役選手の修行(※)に余計な障害は起こらないのです。
※:指導者には「社会的困難や障害、妨害は、本人の捉え方次第で、ある意味”修行”にもなる」というのも人間の哀しさ、人生の深さですが・・・・。
それでも「空」という文字の理念が好きで使っているため、しばしば「空道って新しい空手ですか?」と聞かれることもありますが(笑)・・・・。(【参考】「空道とは」)
最後に。空道がもっともっと普及して、敢えて主張しなくても見ただけで「あれは空道だ!」と分かって貰える (市民権を得る) 日が来たならば、逆に、競技に走り過ぎず「大道無門」というルーツを忘れない為に「大道塾」という名前が復活する日が来るかもしれません。(その時は逆に空道が肩に回るのでしょうか?笑) (掲載日2010.8.21 一部修正2010.8.25)
RE:
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
